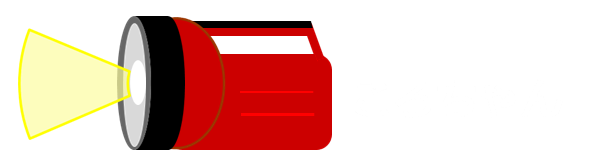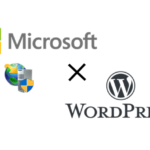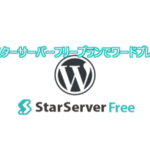2021/09/10

実家にあったナショナルのff-215cpをLED化してみました。単2型電池2本の豆電球タイプの懐中電灯です。

Panasonicのサイトより、詳細確認。赤色タイプが出てます。黄色のこれは検索しても出てこなかったので少し珍しいかもしれません。

Nationalロゴの横にJISマーク。そういえば最近JISマークのついた製品みないな。小学校の時に使っていた鉛筆には必ずJISマークの刻印があったので懐かしいです。この懐中電灯も結構古いのかもしれません。



作り方
懐中電灯のボディ本体は改造せずに、豆電球をLED電球に交換する方法で作ってみることにしました。いらない豆電球の口金を利用し、全ての部品が収まるように検討してみます。電源電圧は電池2本の3V。充電式電池でも点灯するようにしたかったので、2.4Vの入力で、点灯させるLEDは1wパワーLEDクラスの明るさは欲しいところです。
点灯回路に使うLEDドライバは、CL0118Bにすることにしました。部品点数も少なく、値段も安いことが決め手になりました。
秋月電子のデータシートより、性能指標。LEDを並列7個で、185mAとなっているので、パワーLEDでもそこそこ明るく点灯させられそうです。

秋月電子のデータシートより、回路図。CL0118Bとインダクタの部品点数2つです。電球のサイズに収まる必要があるので、部品点数の少なさは大きなメリットです。

今回利用するLEDはCreeのXPGWHTにしました。
利用したLED:Cree XPGWHT-L1-0000-00G53
秋月電子のWEBサイトより:VF:2.95V@IF=350mA、130lm@IF=350mA、3.54×3.45mm
回路の検討をする際に参考にさせていただいたサイト。
データシートの標準回路に、コンデンサとショットキーバリアダイオードを追加するアイデアを取り入れました。
47μHのインダクタを、小型で緑色のアキシャルリードマイクロインダクターと通常のインダクター、またショットキーバリアダイオード・コンデンサの有り無しパターンの4パターンで試してみた結果です。

| パターン | 組み合わせ | LED電流mA |
|---|---|---|
| 1 | CL0118B・インダクター・SBD・コンデンサ | 230mA |
| 2 | CL0118B・インダクター | 210mA |
| 3 | CL0118B・マイクロインダクター・SBD・コンデンサ | 190mA |
| 4 | CL0118B・マイクロインダクター | 170mA |
測定条件:電源は充電式電池2本(計2.7V入力)。SBDは1S4を利用。コンデンサは47μFのチップ型を利用。インダクターは47μH、マイクロインダクターはアキシャルリードタイプの47μH。LEDはCreeXPGWHT。
パターン1の計測時。LEDには230mA流れました。かなり明るいです。SBDとコンデンサと追加すると10~20mA程度多く流れる結果となりました。発熱もあるので、放熱対策は必要ですね。

一番明るく点灯したパターン1にしたかったのですが、インダクタが大きくサイズオーバーで断念。サイズ的に許容範囲であった、パターン3で作ることにしました。パターン3の部品一覧です。

実際に作った回路図です。

汎用的な放熱板を利用。これを豆電球サイズに加工します。

直径12mmに加工。飛び出している部分をあらかたペンチで切り取り、あとは金工やすりで丸く仕上げました。

LEDと放熱板は放熱シリコーンで接着。プラスとマイナスの端子をはんだ付けしました。

部品同士を直接はんだ付け。口金に上手く収まるように、調整します。

LEDとコンバータと口金をはんだ付け。

すき間を放熱シリコーンを充填して固めます。完全硬化まで24時間位かかりました。

オリジナルの電球との比較。

取り付けた状態。


点灯
オリジナルの電球と比較。感覚的には3倍位明るく感じます。LED光源の位置を電球のフィラメントと同じ位置に調整したので、リフレクタに反射しうまくスポットになりました。この撮影で使った電池はすべて充電式の単3電池です(単3→単2変換のスペーサ使用)。


キャンドルモードで点灯。

流れている電流は200mA弱。放熱板と放熱シリコンの対策で大丈夫そうです。1時間位つけっぱなしにしてみたところ、電球全体がほんのり温かくなる程度でした。

まとめ
- 本体は無改造で豆電球のみLED化
- 電球に戻すことができる
- CL0118BとパワーLEDを組み合わせ、少ない部品点数で明るさも実用的なものに仕上がった。
- 昇圧回路のため、電池を最後まで使えて経済的。